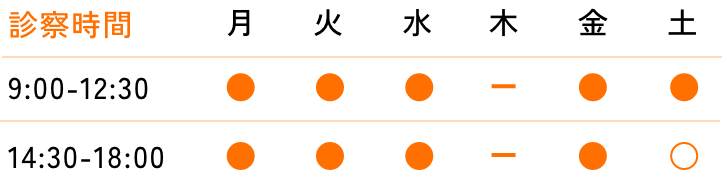中世の新型コロナウイルス対策!?
室町時代の第一〇一代の天皇となった称光(しょうこう)天皇は、20代の若さで早逝しています。
普段、天皇は清涼殿という場所で暮らしていました。ですが、死にそうになると清涼殿を出されて、
黒戸と呼ばれる何もない離れのような小部屋に運ばれて、亡くなるまで安置されるのです。その時代
最も尊いはずの天皇が「出される」のです。ですが、さすがに何もせずにという訳にはいかないので、
護摩を焚いて、ひたすらお祈りを捧げるのです。この時、お祈りしろと言われ指名されたのが、
如意寺満意という僧侶でした。でも彼は祈祷を嫌がったのです。どうせ死ぬとわかっているのに、
「あいつの祈祷はダメだ」と後で後ろ指を刺されるのが嫌だったのでしょう。とはいえ断れず、祈祷
を行いますが、称光天皇は崩御されました。この称光天皇の父は私の大好きな一休宗純の父でもあると
噂されている後小松天皇です。この後小松天皇が息子の葬儀をする際に、遺体を運び出すように命令
しますが、遺体が通った部分については「穢れがあるから」との理由で全て破却してしまいます。
後小松天皇が自分の息子の遺体に対しても徹底した対策をしたのは「穢れ」というものが忌諱される
べきものだったからでしょう。今の感染対策のようなものですね。でも行き過ぎています。
興味深いのは、死人のそばに行き「穢れ」に直接遭遇した場合は「甲の穢れ」を持つとみなされ、
一定期間自宅謹慎を命じられます。「甲の穢れ」を持つ人と接触した人は「乙の穢れ」を持ち、
「乙の穢れ」を持つ人に接触した人は「丙の穢れ」を持つとみなされます。この穢れは一度ついたら
死ぬまで・・・というわけではなく、決められた期間を謹慎すれば消えると考えられています。
こうした「穢れ」の捉え方は、新型コロナウイルスの濃厚接触者に非常に近いものを感じます。
新型コロナウイルスも発症した人を「感染者」として一定期間隔離し、その人と同じ空間にいた人を
「濃厚接触者」とみなして隔離していましたが、まさにこれは「穢れ」を嫌がる感覚と構造がまるで
一緒なのです。感染対策を嫌がるというのは語弊がありますが、やっていることは一緒です。
病原体という発想はないものの通じるものはあったに違いないですね、一休さ〜〜〜〜ん!!