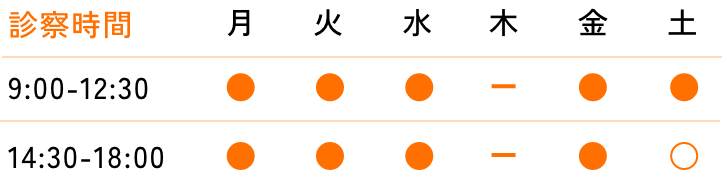ベルツとスクリバの碑
皆さんは東大病院に行かれたことはありますか?私は4、5回行ったことがあります。東京・文京区の
本郷にある東大構内の東大病院前のバス通りに面した小さい公園に2つの胸像が並んだ立派な碑が
あります。胸像だけではなく背景部分も立派なのです。明治時代に建てられた顕彰碑が立派に残って
いるのは少なく、多くの肖像彫刻の多くは戦時中に供出されることが多かったようです。
この彫像は東京大学で内科学を指導したエルヴィン・フォン・ベルツ先生と、外科学を指導した
ユリウス・スクリバ先生の両人が20年以上にわたり近代医学の基礎を築いた恩人なのです。
このお二人の功績を記念するために病院を眼下に見渡せる場所に明治40年4月4日に建設されました。
ベルツ!あ〜あの人ね…とはならないはず。ベルツ水は箱根の旅館の女中のアカギレを見て作った
グリセリンカリ液があります。明治時代の初期にお雇い外国人と言われて、招聘された外国人専門家
の1人なのですが、1876年に日本に到着して東京帝国大学医学部の前身である東京医学校で内科学・
病理学・精神医学を担当したと言います。ベルツは教育者や侍医など臨床医として活躍・功績を
残したのですが、日本人女性のハナと結婚し生まれた娘の臀部に青あざを発見して、”蒙古斑”と
命名したのはよく知られています(1歳ごろには消失します)。ベルツの仕事だったのですね・・・
ツツガムシ病や肺ジストマの発見もしており、ベルツの慧眼とフットワークの良さも伺えます。
さらにベルツは温泉好きであり温泉が持つ病気の治療効果に関心を持っていました。当時は、
東京から草津に行くのには時間がかかり(伊香保温泉が限界)、草津温泉は辺鄙な温泉地に
すぎませんでした(当時ですよ)。ところがベルツは泉質はもちろん、その山の空気と水の良さ
で健康に非常に良いことを見出して、紹介し宣伝したのも彼なのです。温泉日本一を決める催しでも
別府温泉や箱根温泉と1、2位を争うのも実はベルツのおかげなのです。温泉地以外の保養地
などの剪定にも熱心で、身体の弱かった東宮時代の大正天皇に葉山の御用邸を実現したのも彼、
ベルツのお仕事だったのです。ベルツの残した言葉で感銘を受けたのを最後にご紹介させて下さい。
『日本人は西欧の科学的成果を切り取って利用するのに長けているが、自ら科学する心を養うこと
こそが重要』と指摘しています。まさに現代にも通じる名言ですね。