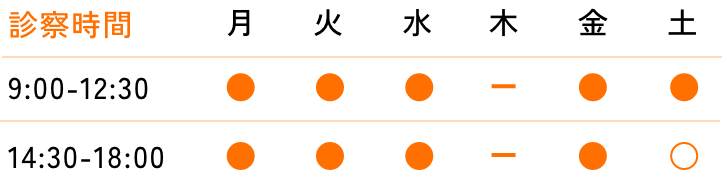今日は何の日?
久しぶりに今日は何の日を考えてみました。6月4日なので虫の日とか蒸しパンの日とかあります。
ここでお話をするので医学的にかかわりがあるのは虫歯予防デーといったところでしょうか。
日本歯科医師会が昭和3年から13年まで実施していたと言います。昭和33年からは当時の厚生省が
6月4日から1週間をを「歯の衛生週間」として復活させたのでした。現代でこそいろいろと歯ブラシ
もありますし、歯磨き粉も充実していますが、江戸時代はどうだったのでしょうか?
江戸時代前期の儒学者である貝原益軒は養生訓の中で「口の衛生」について記載しています。
朝の行事として「牙歯をみがき、目を洗う方、朝ごとに、まず熱湯にて目を洗いあたため、鼻中を
きよめ、つぎに温湯にて口をすすぎ、昨日よりの牙歯の滞(とどこおり)を吐きすて、ほしてかはける
塩を用いて、上下の牙歯と、はぐきをすりみがき、温湯をふくみ、口中をすすぐ事二三十度」と入念!
さらに「毎朝かうのごとくにして、怠りなければ、久しくして牙歯うごかず。おいても落ちず。虫くはず
・・・今八十三歳にいたりて、猶夜、細字をかきよみ、牙歯固くして一もおちず。目と歯に病なし」と
いうように現代で言う「8020運動」先を越していました。江戸時代は柳の楊枝が歯ブラシ代わり
でしたが、彼は推奨しなかったようです。
食後に歯に挟まったものは湯茶で口を吸う回すすぐ事で口の中を清潔に保ちなさいとしています。
楊枝を使うなとしています。彼なりの哲学があるのでしょう。もちろん現代とは食べ物も違いますが、
このようにして83歳まで歯を保っていられるということは、メンテナンスの意味合いも良かったと
言えるのではないでしょうか。「塩磨き、口すすぎ」だけという訳にはいきませんが、その習慣も
見習わなくてはいけませんね。