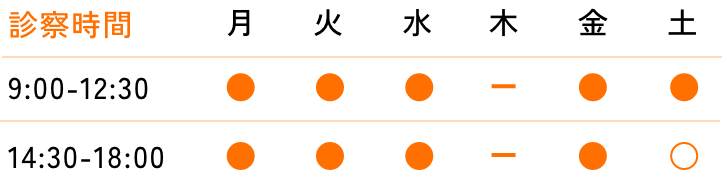吾輩は胃弱である
夏目漱石の「吾輩は猫である」を読んだことがある人はかなり多いのではないでしょうか?主人公の
猫から見た人間観察が面白おかしく書かれています。主人公の飼い主は珍野苦沙弥(ちんのくしゃみ)
という名の中学校の英語教師、性格は偏屈でノイローゼ気味で胃が弱いという特徴の・・・つまり漱石
自信をモデルにしたのではないかと思われます。
もともと「吾輩は猫である」は1回読み切りの予定で「ホトトギス」に掲載されましたが、かなりの
大好評で、11回の連作となったのでした。例えるなら読み切りのジャンプの漫画が好評で連載された
感じと同じでしょう。当時でも相当な人気だったのです。小説の中で「彼は胃弱で皮膚の色が淡黄色を
帯びて弾力のない不活発な徴候をあらはして居る。其癖に大飯を食ふ。大飯を食った後で
「タカチヤスターゼ」を飲む。飲んだ後で書物をひろげる。二三ページ読むと眠たくなる。涎を本の上
へ垂らす。是が彼の毎夜繰り返す日課である」ここにでてくる「タカチヤスターゼ」は高峰譲吉が特許を
とったタカジアスターゼのことで胃腸薬のことです。胃もたれ、胸やけの薬として使われたのです。
漱石自身も実際に使っていたようです。「吾輩は猫である」に続いて、「倫敦塔」や「坊ちゃん」を
発表した後、明治40年教職をやめて朝日新聞に入社し職業作家として道を歩き始めました。塔
そのとき、京都大学教授のポストを蹴っていたようです。すごい!!
ところが、明治43年6月に「門」執筆中に胃潰瘍で入院。療養中の修善寺でも大量吐血をして生死を
彷徨います。胃潰瘍での入退院を繰り返し大正5年12月に帰らぬ人となったのです。
漱石の死から2年後に胃潰瘍の手術が行われるようになり、昭和57年に登場した胃酸を抑制する薬で
胃潰瘍の出血が激減し、ほとんど手術が不要になったのです。漱石が活躍した12年間の間に治療法が
確立していれば、もっともっと多くの作品が読めたかもしれませんね。