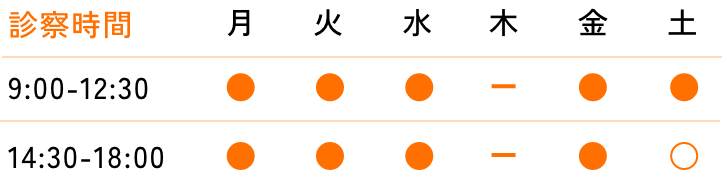2025.11.19
打診法の発明

17,18世紀ヨーロッパの医師は、患者の言葉を聴きながらその表情や態度を観察すること
で診断していたようです。そんなことできる?と思いませんか?もちろん検査のない時代
です。患者さんに直接手を触れるのは医師として品位を落とす行為で、床屋外科医のする
行為だったのです。内科本道、外科外道という時代ですから・・・元外科医としては悲しいです。
この時代、問診は別としても、視診、触診、打診、聴診のいわゆる4診のなかの視診と
脈をとると言った限られた触診で診断し、打診と聴診は知られていなかったのです。
オーストリアのレオポルド・アウエンブルッガーは当時最先端の医学をウィーンで学び、
7年間の研究の末に、1761年、「新考案ー身体を指先で叩いて出る音から、内部の臓器の
健康状態を測るー」という著書を残し、打診法という検査方法を発表したのです。
このアウエンブルッガーという人のすごいところは、「患者が話す症状は信用できないし、
医師が観察する外見的病状も確実性に欠ける。身体から聞こえる病的な音こそが、胸部疾患の
性質や進行状況を見るのに最も信頼できる手掛かりになる」という、現代の我々にも喝を
入れられているようなお言葉を残されています。つまり、従来(昔)の診断方法に代わる
信頼性の高い診断法で肺疾患の診断を根本的に変えるものと自負したのです。
ですが、打診法はなかなか採用されませんでした。やはり患者に触れることの忌避のためです。
アウエンブルッガーは1722年の今日11月19日に生まれましたが、旅宿だった自宅で父親が
常々ワイン樽を叩いて残量を調べていたことにヒントを得て打診法を考案したと言われて
いますが、どうやら作り話のようです。