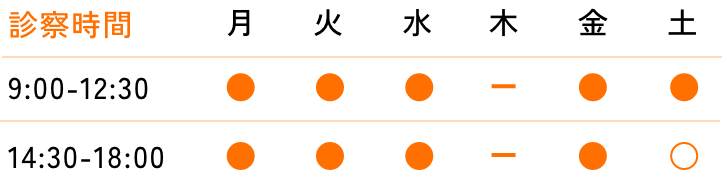極端性の回避
皆さんは毎日の食事や、欲しいものを買う時に、常に高いか安いかを判断して買い物をしています。
そのものが絶対欲しい!という状況でなければ、それが他と比べて高いか安いかが結構重要な
判断材料になっているのではないでしょうか。
例えば、天丼を食べに行ったとしましょう。2,000円の「上」と1,000円の「並」があったとします。
その時は、安い方を選ぶ人が多いのではないかと思います。そこに1,500円の天丼があったのならば
多くの人は、真ん中の1,500円を選択するのです。これを極端性の回避と言います。
日本では松竹梅効果とも呼ばれることがあります。この極端性の回避については、いくつかの理由が
考えられます。そのもの自体の価値を見極めるのが難しい時に、他と比較して価値を判断するのです。
これにより、真ん中のグレードを選択すれば、それ相応の価値は見込めえるだろうという気持ちが
生まれて、真ん中を選ぶようになります。もう一つは、損失の回避です。もし一番高いものを買って
、その性能や料理であれば値段にそぐわない状況であると損失が大きいように感じてしまいます。
その点、真ん中のグレードであれば、それなりの性能やおいしさが保証でき、あるいは期待できるので
失敗しても大きな損失にはならない気持ちになるのです。通常私も知らないうちに極端性の回避をして
いました。ところがうちの長男は、必ず松竹梅であれば迷わずして「松」を選択するのです。
まぁ小さいうちは仕方ないなぁと思っていましたが、専門学校に入学してもまだその考えには変化が
ありません。彼には相対性がないばかりか、損失回避というものが欠如しており、逆に極端性を求めて
いるのです。「どうしてそのステーキを選ぶの?」の問いには「高いから」とのことです。
もはや、確信犯!働き出したら奢ってもらい、将来は介護してもらいます。笑