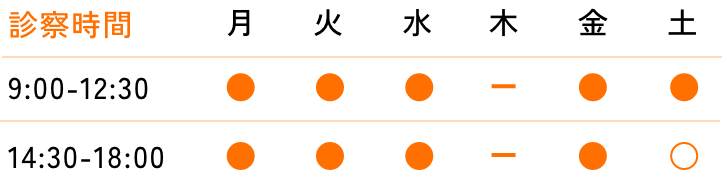75歳を境に病気のリスクが上昇!
内閣府の調査でも要介護、要支援の認定を受けた人の数は増加しており、特に75歳以上で
その割合が高くなると報告されています。認知症では中年期の肥満がリスク因子ですが、
75歳以上では反対に体重減少が引き金になるのです。75歳以上になると、一つではなく
複数の病気を併せ持つことが多くなり、それゆえ、治療で使用する薬の副作用が生じやすくなる
などの変化も起きてきます。75歳以上であれば一つの病気を治療しても回復困難であり、反対
にかえって身体機能が下がり、要介護や死亡のリスクを高めてしまうことも少なくありません。
このような独特の身体的状態を考慮して高血圧については75歳以上の高齢者の高圧目標値は
やや緩めに設定されています。糖尿病でも、75歳以上になると、高血糖に起因する死亡リスクは
74歳以下までと比べて軽度となる研究もあります。治療意欲を喪失させるかもしれませんが、
70歳以上を対象とした研究では、LDL(悪玉)コレステロール値が高いことと冠動脈疾患の発症
には関連性がないとされる報告が多いのです。このように75歳を境にして身体機能の低下の仕方
とか病気のリスクは大きく変わるのです。それは75歳を境に老化が急速に進行すると言うことでも
あります。日本老年学会・日本老年医学会が提唱した65〜74歳を准高齢者、75歳以上を高齢者と
定義する概念根拠の一つにもなりえます。では、なぜ65歳以上を高齢者の基準としたのか?
それは、100年以上前にドイツ帝国で国民に年金を支給する制度を作るにあたって、宰相ビスマルク
が、それ以上長生きして年金を受給するものはほとんどいないはずだと考えて、65歳と言う年齢
を設定したのが始まりだとされています。つまり65歳以上まで生きる人の方が少なかったのです。
100年後、その年齢が「高齢者」の基準にも満たなくなる社会が訪れようとは、鉄血宰相も想像
できなかったのでしょう。