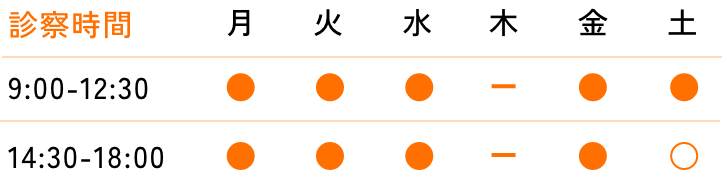AKBじゃないよTKGだよ

江戸時代の川柳に貴重な句が残されています。吉原の遊郭を詠んだものとされています。
「吉原を四方に歩く玉子売り」
「生卵北極ほどな穴を開け」わかりますか?吉原では夜の見世開きと同時に、玉子売りと
鮨売りがやってきて、精がつく食べ物として生卵とゆで卵を買い求めたそうです。
後者の句は生卵のてっぺんにかんざしなどで、地上から見える北極星の大きさほどの小さな
穴を開け、直接中身を吸い取った情景を読み取れます。当時は薬食一如の食べ物として、
貧弱な食生活の中では珍重されていたとされます。江戸時代中期の料理書「素人包丁」には
すでに現在の卵かけご飯に近いと思われる献立が載っています。釜で炊いたごはんに溶いた
卵をかけたごはんです。日本には元来、納豆やとろろ、モロヘイヤ、ウナギなどのように
ヌルヌル、ネバネバした食べ物を好む和食文化があります。卵も卵白のネバネバが共通して
います。日本人の主食のごはんをどのようにして美味しく食べるのかの工夫が、このネバネバ
の生卵を使った卵かけごはんとなったのです。まさに、ここに卵かけごはんの原点があると
言っても過言ではないでしょう。
生卵に関する記録として、大石内蔵助をめぐる「おれの足音」の中で池波正太郎は次のように
描出しているのが印象的です。いよいよ吉良邸に内入りする当日、赤穂浪士たちは「堀部安兵衛
宅へあつまった(旧暦1702年12月14日、新暦1703年1月20日)。大石内蔵助と主税の父子が
あらわれたのは夕暮れ少し前だった。堀部安兵衛の親友で、学名高い細井広沢が、生卵を
たくさん抱えて激励にあらわれた」というのです。内蔵助をはじめ一同は、何よりも鴨肉入り
生卵をかけた温かいごはんを大喜びで食べたといいます。ですが、この逸話を裏付ける資料や出典
は不明であり、全員ではなくとも両国のそば屋で蕎麦を肴にして最後の宴を開いたという説もあり
ます。もしかすると、親子丼付きの池波さんの気持ちで討ち入り直前の大石らに卵かけご飯を
食べさせたのかもしれませんね。とは言っても、私個人的には当時は生卵が活気をもたらす強壮剤
として食べられていたことが伝わるとともに、話の展開から討ち入り前に食べるにふさわしい食材
として、池波に書かしめた卵の凄さを改めて感じさせてくれます。