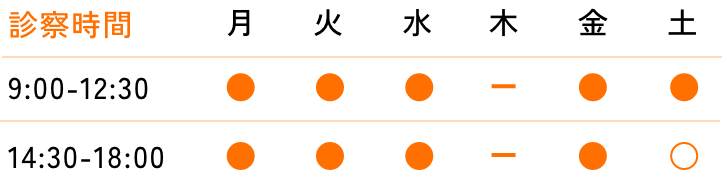認知症

認知症とは
認知症とは、正常に発達した脳の働きが、さまざまな原因によって持続的に低下し、記憶や思考、判断力、言葉の理解、日常生活の動作などに支障が生じる状態を指します。加齢によって物忘れが増えることは誰にでもありますが、認知症では「昨日の食事を覚えていない」「財布をしまったこと自体を忘れる」「料理の手順がわからない」といった生活に支障が出るほどの症状が現れます。単なる老化による物忘れとは異なり、進行すると介助が必要な状態になることもあります。日本では高齢化が進むにつれて患者数が増加しており、2025年には約700万人、65歳以上の方の5人に1人が認知症になるといわれています。誰にとっても身近な病気であり、本人だけでなく家族や社会全体で支えていくことが大切な病気となります。
認知症の主な種類
認知症にはいくつかのタイプがありますが、代表的なのは次の4つです。
①アルツハイマー型認知症
最も多いのがアルツハイマー型認知症で、全体の約6割を占めます。脳の神経細胞が徐々に減少し、記憶を司る海馬の萎縮が見られます。初期には記憶障害が目立ち、「同じことを何度も聞く」「約束を忘れる」などの症状が現れ、次第に言葉や判断力にも影響が出てきます。
②脳血管性認知症
次に多いのが脳血管性認知症です。脳梗塞や脳出血などによって脳の血管が詰まったり破れたりし、その部分の脳機能が損なわれることで起こります。症状は「まだら」な傾向があり、調子の良い日と悪い日があるのが特徴と言われています。また運動麻痺や言語障害を伴うこともあります。
③レビー小体型認知症
レビー小体型認知症は、脳内に「レビー小体」という異常なたんぱく質が蓄積して起こります。特徴的なのは、実際には存在しないものが見える「幻視」や、手足の震え・動作の遅れなどパーキンソン病に似た症状が現れることです。注意力の変動が激しく、ある時間帯はしっかりしていても、数時間後にはぼんやりするなど、状態が変わりやすいのが特徴となります。
④前頭側頭葉変性症
前頭側頭葉変性症は、人格や社会性を司る前頭葉や、言語を司る側頭葉が障害される病気です。感情のコントロールが難しくなり、怒りっぽくなったり、反対に無関心になったりします。言葉が出づらくなる失語症を伴うこともあります。比較的若い年代(50~60代)で発症することもあります。
認知症の主な症状
認知症では、まず「記憶障害」が現れます。数分前の出来事を忘れてしまう、同じ話を何度も繰り返すといった症状が見られます。次に、「見当識障害」といって、今がいつなのか、どこにいるのかがわからなくなることがあります。時間の感覚が曖昧になり、夜中に起きて「朝だから出かけなきゃ」と言い出す場合もあります。また、「判断力の低下」や「理解力の低下」も特徴的です。買い物の支払いで混乱したり、ガスをつけっぱなしにしてしまったりと、日常の安全にも影響します。さらに進行すると、「感情や性格の変化」「被害妄想」「徘徊」などの行動・心理症状(BPSD)が現れることがあります。一方で、本人は初期のうちは自分の異変に気づいて悩むことが多く、うつ状態になる方もいます。家族が「年のせい」と片付けてしまうと、適切な治療の機会を逃してしまうため、早めの受診が大切です。
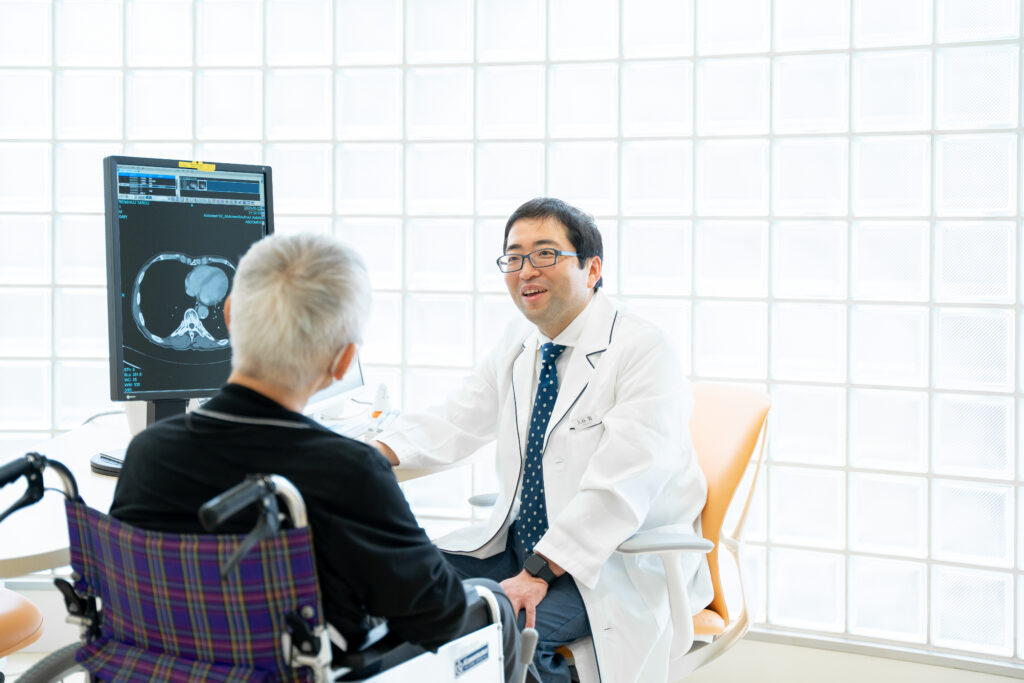
認知症の診断
認知症の診断では、まず問診と心理検査が行われます。代表的なのが「MMSE(ミニメンタルステート検査)」などのテストで、記憶力・注意力・計算力などを評価します。さらに、CTなどの画像検査で脳の萎縮や血管障害の有無を確認します。アルツハイマー型認知症では海馬の萎縮が、脳血管性認知症では小さな脳梗塞の跡が見られることが多いです。近年では、脳内の異常たんぱく質を可視化する「アミロイドPET」などの検査も行われるようになっています。認知症と似た症状を示す「せん妄」「うつ病」「甲状腺機能低下症」「ビタミン欠乏」などの病気もあるため、鑑別診断も重要です。これらは治療によって改善する可能性があるため、自己判断せず専門の診察を受けましょう。
認知症の治療
残念ながら、現在の医療では完全に治す治療法は確立されていません。しかし、進行を遅らせたり、症状を和らげたりすることは可能です。
アルツハイマー型認知症には、アセチルコリンという神経伝達物質を増やすコリンエステラーゼ阻害薬(ドネペジルなど)や、神経細胞の興奮を抑えるNMDA受容体拮抗薬(メマンチンなど)が使われます。これらは記憶や注意力の低下を緩やかにし、日常生活を維持する助けになります。また、生活環境の整備やリハビリも大切です。慣れた場所で安心して過ごせるように家具の配置を変えない、予定をカレンダーに書く、写真やメモで記憶を補うなど、環境を工夫することで不安や混乱を減らすこともできます。また、デイサービスや認知症カフェなど、地域のサポートも積極的に利用しましょう。
認知症の予防
認知症の発症には、生活習慣が深く関係していることがわかっています。高血圧・糖尿病・脂質異常症・喫煙・運動不足などは、脳の血流を悪化させ、発症リスクを高める要因です。つまり、生活習慣病の予防こそが認知症の予防につながります。
有酸素運動(ウォーキングや軽いジョギング)は脳の血流を良くし、神経細胞の働きを保つ効果があります。また、人との会話や読書、計算、料理など、脳を使う活動も効果的です。新しい趣味を始めることや地域活動に参加することも、脳の刺激になります。食生活では、魚に含まれるDHA・EPA、緑黄色野菜、果物、ナッツなどをバランスよく取り入れることが勧められています。
さらに、睡眠も大切となります。深い眠りの間に脳内の老廃物が排出されるため、質のよい睡眠を確保することで認知症のリスクを減らすと考えられています。

家族の支えと社会の理解
認知症は本人だけでなく、家族の生活にも大きな影響を与えます。介護する側が疲れ切ってしまわないように、行政や地域の支援制度を積極的に利用することが大切となります。介護保険サービスを活用すれば、訪問介護やデイサービス、ショートステイなどを利用して負担を軽減することも可能です。また、本人の尊厳を守ることも重要です。できることはなるべく本人に任せ、成功体験を積み重ねるようにしましょう。否定的な言葉ではなく、「一緒にやってみよう」「ゆっくりで大丈夫だよ」といった温かい声かけも支えになります。現在、多くの自治体では「認知症講座」などが行われ、地域で見守る体制づくりが進んでいます。
認知症になっても安心して暮らせる社会を築くために、ひとりひとりの理解と協力が欠かせません。ひとりで抱え込むことなく医療機関に早めに相談をしましょう。
認知症で悩みがあるご家族の方へ
認知症は誰にでも起こり得る病気ですが、早期発見・早期対応によって進行を遅らせることが可能です。物忘れが気になったときには我慢せず、かかりつけ医や専門医に相談してください。生活習慣の見直しや社会的なつながりを大切にすることが、予防にもつながります。医療・介護・家族・地域が連携することで、ご負担も軽減することができます。
また、必要に応じてより高度な治療や検査を行う場合には、近隣の専門医療機関にご紹介をさせていただくことも可能です。まずはお気軽に当院までご相談ください。